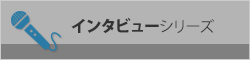2012年9月~12月、日本能率協会エグゼクティブビジネスリーダーコースにプログラムコーディネーターとして参画。18社24名の異なるバックグラウンドを持った受講生の互学互修をプロデュース。3種類のアセスメント(自己分析、360度フィードバック、ビジネスシミュレーションゲームでの専門アセッサーによる診断)、経営者講演、財務・マーケティング・経営戦略・人事の専門知識講義などがメインプログラム。自社に閉じず、他流試合で相互研鑽を図る4ヶ月であった。(平均年齢49歳)
海外赴任前研修
某消費財メーカーにおいて、海外赴任前研修を行った。2011年11月~2012年9月のロングラン。 赴任前年におけるプログラムデザインおよびその運営を担当。英語プレゼンテーショントレーニング・異文化適応トレーニング(セルフアウェアネス、ステレオタイプ診断、異文化下での情動コントロール法など)、社内&社外赴任経験者による講演、赴任国の事前スタディー(仮説→検証スタイル)、赴任予定者の月毎振り返り(月毎個人レポートへのフィードバックコメント)などを行った。帰任時に一回りも二回りも大きくなっていることを願うばかり。
アクションラーニング研修
某医療機器商社にて、2013年5月~8月にてアクションラーニング研修を実施。経営幹部候補15名を5名三組に分け、社内の重要課題をテーマにとりチームで討論。課題解決フレームワークに沿って、社内他部門のメンバーとディスカッションプロセスを互学互修で進めていった。最終発表は社長に対して実施。「通常現場業務での経験知・暗黙知を形式知化するうえで役立った」「社内ではあるものの他部門の考え方が新鮮で刺激になった」といったコメントがあり、多くの相互啓発が誘発されていた。
コンピテンシーインタビュートレーニング
某外資系日本法人にて、コンピテンシーインタビューを構造的に実施するためのトレーニングを行った。 ガイドラインの変更がグローバルであり、ニューヨーク、シンガポール、ロンドン、東京で同タイミングで実施。 東京オフィスにおいては初導入のため、講義・ロールプレイ・ディスカッションを丸一日かけて行った。
四方良しとエグゼクティブサーチ
Win-winという言葉があるが、いまだどうにも馴染めないでいる。
相手と自分との双方が良い状態を作ること、という意味であるが、そこに「社会」が入っていないのがその理由である。少々狭いのではないかなぁ、と。
そういう意味では近江商人が大事にしている「三方良し」という基本コンセプトには
大いに共感する。相手と自分、そして社会の三つの要素がともに良くなっていくシステムは好循環を生み、サステイナブルな状態を創り出していく。登場人物が全て舞台に上がってすっきりした気分だ。
ではエグゼクティブサーチとはどういう状態を求めることができるプラットフォームなのだろうか?
プレイヤーは、依頼人(多くの場合は企業)、移籍する人、社会、そしてエージェント、である。
あるプレイスメントが成立する事で、その企業にとって追加的価値が創造され、移籍した人もそこで達成感や経済的な利得を得ることができ、そしてそれが企業法人税額の増額に貢献していたり、モノ・サービスが社会的にも意味がある場合、社会にとってポジティブなインパクトを与えたことになる。そしてエージェントも適性な利得と満足感を得る。
そのような「四方良し」の状態を目指す・目指せるのがエグゼクティブサーチというプラットフォームの良い点である。
「四方良し」のプレイスメントをどれだけ紡ぎだせるか、がこの世界に入った時の問題意識であり、今もそこへ向けて研鑽するばかりである。
(細腕ゆえなかなか至らず、そんな自分に困惑する毎日でもある・・)
社長記者会見・疑似体験研修
先日、JMA(日本能率協会)主宰の「部長のためのマネージメントコース」にコメンテーターとして参加をしてきました。一部上場企業の精鋭・経営幹部候補20名(40代後半)が集まって、戦略経営論に冴えを見せる神戸大学・三品教授のイニシアティブで切磋琢磨。その10回(10ケ月)コースの最終日。卒業イベントとして、「数年後に自身が社長になったとしての記者会見」をイメージしきって “10分就任演説+20分質疑応答”、という内容。 そして私の役どころは記者として「厳しい質問を突き付ける」というもの。JMAさんによる「場の設営」は本格的で、経団連会館の会議室に6~7基ほどの報道用ビデオカメラを据え、カメラのフラッシュも常時浴びせ、受講生は相当な“なりきり感”をもって臨んでいました。
ライティングの熱気もあわせ、皆さん汗だくで真剣に会見でメッセージを発し、そして間髪入れずの会見後・質疑応答タイムでは、 「なぜ時価総額が低迷しているのか?」 「グローバル競争で勝ち抜ける“個人”は育っているのか?」 「なぜ選ばれたと考えるか?使命は?」 といった矢のような質問にも各人各様のスタイルで答えておられました。30分を乗り切ったころには“ホッとした顔”を浮かべる方もいれば、“覚悟”が腹に落ちたたたづまいの方も。 10ケ月研修のうちに中東赴任となったプラントエンジニアリング会社の方など、修羅場をくぐった野武士のように実に堂々と対応されていました。
Future Pullという技法があります。それは、未来のあるべき自分を「語ること」で強く自覚(固着)し、それと現在の自分との差を内発的に意識し、その未来へ自身を引っ張られていくようしむけるもの。JMAさんの場のしつらえはその記憶固着力を強める為でしょうし、かなりパワフルに体験が脳に入ったのでは、と。 今後、折に触れて “振返り(reflection)” をそれぞれが行う際にも社長目線で発したメッセージの記憶が鮮明に蘇るのではないでしょうか。ミドルマネージメントから役員に向かわれる手前でこのような機会がもてるのはとてもポジティブなインパクトを個人の成長にもたらすように感じました。
この10回研修において、インドを訪問し現地企業社長と「グローバル社会の現実をどうみるか?」をテーマに意見交換をしたり、先達(三菱ケミカルHD社長、セコム会長、花王顧問、等そうそうたるメンバー)による講演を聞いてディスカッションを行ったりで、事業観・人間観・歴史観・世界観を付けるための深い仕掛けが張り巡らされていました。社長記者会見も含めてこれらの研修効果を活かすには日々の活動と如何に紐づけていけるかでしょうし、受講生みなさんの日々の研鑽とうまく連結されていくよう願うばかりです。
成功体験の影響力
成功体験(サッカ―)
南アフリカワールドカップの熱狂が一段落し、新生日本代表がイタリア人・ザッケロ―ニ氏を招いてスタートをした。ホームとはいえサッカー大国アルゼンチンを1:0で下し、アウェイでの韓国戦を引き分けに持ち込んだ。上首尾なスタートと言えよう。 長年のサッカ―ファンとしては嬉しい限りである。
マスコミは『ザックの魔法』などと新監督を褒めそやしているが、やはり岡田監督が今年前半でもがき苦しみ、最後の最後で活路を開いた「コレクティブな守備」「球際で勝つこと」といった大舞台で得た体験・記憶がポジティブな形でインパクトを与えていると思う。その上にたってこそ、「縦へ(前へ)の意識をもっと!」というザッケロ―ニ監督の指示が良い化学変化を生みだしているのであろう。
そして何より、自国開催以外で初めてグローバルでのベスト16に入った、という成功体験からくる自信が大きく物を言っているように感じられる。 これほどに変わるものなのか!と驚嘆に目を見張る思いである。
「負けてもいいから日本らしいサッカー、質の高いサッカーを見せてほしい」という意見がワールドカップ前にチラホラ見受けられた。大会中も著名なサッカ―コラムニストが舌鋒鋭く岡田監督の手法を批判し続けていたが、それは全くの見当違いというもので、ワールドカップとは疑似戦争のような勝敗にこそこだわるべきものと私は思っている。そして、勝つことによってしか得られない自信がどれほど次への糧になるかは今回のザックジャパンによって大いに証明された気がする。
南アW杯までの日本代表は、ブラジル・アルゼンチン・スペインなどの大国を相手にすると、不必要なほどに相手をリスペクトしすぎ「勝とうとする意志」が感じられないことが多かった。戦わずして気持ちで負けている感じ。 それが今回のアルゼンチン戦では微塵も感じられず全員がファイトをしていた。南アW杯ベスト16に食い込むことで、長年日本サッカー界に巣食っていたメンタル面での負のバリアーがようやっと取り除かれた気がしたのは私だけであろうか。
成功体験の持つ大きな効果を再認識するこの二試合であった。
****************
失われた20年、という表現が日本経済に対してよく使われる。それがもたらすインパクトとして、成功体験を十分に持ち得ていない若手層がドンドン増えているという事実が挙げられる。自分に対して自信が持てない、思い出せる成功体験がない、というのはかなりつらいものである。対して、中国等新興国においては成功体験を持つ(失敗も!)若手がドンドン産み出され、実力以上の勢いを獲得しているように思われる。現状、彼我の差は大きい。
ある雑誌に載っていた証券会社スタッフのコメントで「最近外国人の日本株買いに勢いがなくなっている。理由を問うと“日本の若者の目には輝きがなくどんよりした印象を受ける”」というものがあった。我々が失い続けているものはとても大きいように思う。
日本サッカ―界もメキシコ五輪銅メダル以来ずいぶん長いトンネルをくぐってきている。そして、ドーハの悲劇・ジョホールバルの歓喜・日韓W杯ベスト16・ドイツW杯惨敗、と徐々にステップアップしてきて、今回「勝つことにこだわって成功体験を得た」段階にようやく入ったわけである。
日本社会も「勝つことにこだわり、成功体験をもった若者の数を少しでも増やしていければ」、などとサッカ―観戦をしていて思った次第である。 (2010年10月28日@ポーランド)
“当てること” と “当たること”
弓道を教えていた祖父から多くのことを学んだ。
「当てる」と「当たる」の違いもそのひとつ。
30メートル向こうの的に向けて矢を射て当てる、至極シンプルなスポーツ。門下生となったのは高校生の頃。
こちらとしては「当てたい」一心で日々練習に励むわけだが、祖父からは
「弓の的に矢を当てようとしてはいけない。結果として自然に“当たる”ようになるまで毎日毎日練習するように」と、何度も何度も口を酸っぱくして教え込まれたものである。 当時まだ若かったため、色気ムンムンで試合などに臨んでしまうのだが、すぐに見抜かれて“的当てゲームがしたいなら、縁日の射撃ゲームにでも行け”と手厳しくたしなめられていた。祖父にとってそれは“スポーツ”ではなく、弓の“道”を学び続ける行動だったのだろう。
祖父の言を現在の仕事に引き寄せた場合、プレイスメントを「決める」 と 「決まる」のニュアンスの違いになる。
ご縁というのは不思議なもので、決めようと無理を通すと、するっと逃げてしまうもののようである。或いは、後で難儀が待つことになる。 対して、決まる御縁は自然にそうなるもの、という「覚悟」でいると状況がそうなっていくように思う。
ここは重要なポイントな気がしている。
自身の軸がぶれていないかどうかを祖父と心の中でよく会話をするのだが、生きていたらなぁ、話をしてみたいなぁ、と最近よく思う。