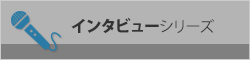このところ、とある特定のスターバックスに頻繁に行くようになった。多くのカフェの中で、数あるスターバックス店舗の中で、何故そのお店に自分は行ってしまうのか?理由はお店の方達が「留岡さん」と名前で呼んで会話をしようとしてくれるから。
20分2000円というスタイルの美容院に行っている。QBハウス的な運営ゆえ、行く度に違う職人さんにカットしてもらっていた。ある日「留岡さん」と名前で呼んでくれる職人さんに出会い、それ以来その職人さんを指名して(若干の指名料)伺うようになっている(他の職人さんにはそのような習慣は無い様子)。
サービス・商品の質に大きな差異を見いだしづらい昨今、「違い」を産み出すポイントのひとつは顧客を「名前で呼びかけ」てコミュニケーションのパス交換を行うことなのだろう。名前を呼んでもらうことで他の客とは違う特別感を演出、という観点には響かない。響くものは、真正面から私をみてパスを出そうとする相手の意志、そしてビジネスライクな価値・対価(ギブ&テイク)とは別種の「感情の関わり・パス交換」へのほのかな信頼。
英語には「仕事」の呼び方が幾つも存在する。Job,Work,Laborなどなど。その中で「Calling」という呼称を私は気に入っている。正しい語源は定かではないが、呼ぶこと・呼ばれること、を仕事の真ん中に据えておきたいと思っている。
名前で呼び掛けられる
PDDRの重要性~一つ目のD
世のビジネスパースンが学ぶイロハにPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Action)がある。このサイクルには明示的暗示的に様々なエッセンスが詰め込まれており、私もこの方法から多くを学んだ一人である。特に仮説→検証(反証)→再アクションの流れを意識するかしないかは、行動の質を上下する大きな分水嶺である。
一方で、「Decide(意思決定)」の要素がこのサイクルにおいて“暗示”にとどまっていることが惜しまれる。
意志決定のメカニズムについて黄金ルールは存在しない。「正しい意志決定などはなく、タイミングと修正のスピードが大切」、とも考えられるが、ひとつの型を学びそれを自分なりに試行錯誤・アレンジして、“自分流”の意志決定お作法をセットアップしておくことはビジネスパースンにとって肝要なことと考える。Plan→Decide→Do→Reflection(振り返り・Check)といった風に、プロセスに「Decide」を明示的に入れこんで捉えてみたい。今年はこの「Decide(意志決定)」の部分を深く掘り下げる一年にしようと考えている。
大晦日
今日は大晦日。年の瀬からこの一年を振り返るに、「多くの人に助けられて」一年があっという間に過ぎていった、という想いが強く残る。多くの人々の支援、様々なお客様からのご愛顧にて今日の私が居る。皆々様、有り難うございました。
来年も「ヒトと組織の成長・発展に貢献する」よう更に努めますので、どうぞよろしくお願いいたします!
Negotiation & Influence Training (欧州系製薬会社)
ベルギー資本の組織開発ファームからの委託で欧州系製薬会社東アジア地域のメンバーにトレーニングを行った。テーマはNegotiation & Influence Training。2014年5月28日―29日の二日間。対象は東アジアチームの30名(日本法人、韓国法人、中国法人から)。ビジネスパートナーのアメリカ人(メイン)とともにCo-Facilitatorという立ち位置。日本人受講生にとっては異文化適応トレーニングの一環にもなった様子。
http://the-blue-ocean-company.com/en/Our_Team
アセスメントが持つパワー
2014年4月、日系電機メーカー人事部員を対象にアセスメントに関するレクチャーを行った。キーワード:Predict(予測)目的とAwakening(人材開発・気づき)目的 等
創造性を喚起するマネージメント
2014年2月、日本能率協会主催のイベント(KAIKAコンファレンス)にて、「創造性を喚起するマネージメント」というテーマで東京大学・渡邉克巳先生(東大先端科学技術研究センター http://www.fennel.rcast.u-tokyo.ac.jp/profilej_kw.html)と対談を行った。先生のご専門は認知科学でバイオロジカルモーションなどの研究をされている。キーワード「潜在意識メカニズムの解明および顕在意識との相互作用」「親近性と新奇性」「無意識と体の共犯性」など。 認知心理科学の視点からビジネス世界での諸事象(イノベーション等)を語っていただいた。
次世代幹部・人財開発~パーソナリティーアセスメント活用
次世代幹部・人財開発を実施するアセスメント会社のプロジェクトに参画。 パーソナリティーアセスメント、360度フィードバック、コンピテンシーインタビュー(2時間)などを元に個々人をプロファイリング。そのデーターを元に今後の自己開発課題抽出と個人へのフィードバック、および社長・経営陣への提言を行った。
法政大学大学院にて講義「労働市場」
2013年5月、法政大学大学院・政策創造学科にて「労働市場」についての講義をテスト講師として行う。石山恒貴准教授の「雇用政策」カリキュラムの一部として担当。聴講は社会人10数名。企業の第一線で働く方々との貴重なインタラクションの機会であった。
コミュニケーション研修~Walk in the dark
 2013年4月、浜松の某CADソフトメーカーの年度初めキックオフミーティングにて研修を実施。アイマスク着用でA会議室からB会議室へ5人一組で移動するシンプルな研修。3チームに分かれ作戦会議、そしてリーダーの指示のもと様々な障害物を避けながら目的地へ。 「視覚が使えない中、如何に言葉を使った正確なコミュニケーションができていなかったか痛感した」 「正確に聴き取る、という基本を怠っていることに気付いた」「漫然とした指示ではメンバーはバラバラ方向に進んでいくのみだった」「事前の作戦会議の重要性に後から気が付いた」といったコメント。 体験ワークの後に、個々→チーム内→全体で振り返り。 コミュニケーションの在り方、リーダーシップ、フォロワーシップなどについて認識が深まる時間であった。
2013年4月、浜松の某CADソフトメーカーの年度初めキックオフミーティングにて研修を実施。アイマスク着用でA会議室からB会議室へ5人一組で移動するシンプルな研修。3チームに分かれ作戦会議、そしてリーダーの指示のもと様々な障害物を避けながら目的地へ。 「視覚が使えない中、如何に言葉を使った正確なコミュニケーションができていなかったか痛感した」 「正確に聴き取る、という基本を怠っていることに気付いた」「漫然とした指示ではメンバーはバラバラ方向に進んでいくのみだった」「事前の作戦会議の重要性に後から気が付いた」といったコメント。 体験ワークの後に、個々→チーム内→全体で振り返り。 コミュニケーションの在り方、リーダーシップ、フォロワーシップなどについて認識が深まる時間であった。