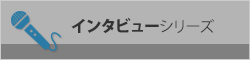グローバルインタビューシリーズの第二回は大澤佳雄さん。IBJインターナショナル(ロンドン興銀)の社長、みずほ証券の社長などを歴任された方です。国際経営者協会でお話を聞いて以来すっかりファンになり、今回のインタビューをお願いしたところ、ご快諾をいただき、インタビューが実現しました。
*
大澤佳雄(おおさわ・よしお)さんプロフィール
株式会社許斐・取締役会長。学習院大学政経学部卒。
IBJインターナショナル(ロンドン興銀)社長、日本興業銀行取締役証券業務部長、同常務取締役(証券業務、国際業務管掌)を経て、興銀証券副社長、みずほ証券社長を歴任。 IBJインターナショナルplc.(ロンドン興銀)在任中にはSecurities and Futures Association, International Primary Market Association, Euro Clear などのボードに参画、みずほ証券在任中には日本証券業協会理事、東京証券取引所自主規制委員会委員長などを歴任。
現在、日本水産取締役、YKK監査役、日本投資環境研究所顧問、日本産業パートナーズ特別顧問。
2007年6月に株式会社許斐の顧問となり、同9月会長に就任。
(以上、株式会社許斐ホームページより)
*
◆自己確立が大事
――私自身(留岡)の問題意識として、「内需だけでは日本はやっていけない」ということがあり、どうしたらグローバル化を進めグローバル人材を輩出できるのかということを常に考えています。それでまず、グローバル・リーダーはどういう条件で育つのかといったあたりからお話を伺えればと思います。
自己確立している人、つまり人間社会の中で自分がどのような役割を持っているかの自覚をもつことが、グローバルな仕事をやる人には必須の要件ではないかと思います。日本でやってきた業務面でのスキルは当然必要ですが、それ以上に人種を超えて人を引っ張っていくことに挑戦する覚悟ができている人が行くと、海外でうまくいくことが多いと言えます。そして、仕事の上でも人間関係の作り方においても自分自身の軸が確立していることが大切ですが、同時にもう一度現地に行ってしかるべき新しい業務環境の中で自分のポジショニングをつくり直すというくらいの度量を持っていることも大事です。
逆に、海外現地法人などの社長に任命されて、自分というもののメリット、デメリット(バリュー)に自覚がないまま、英語でいうナイーブとかイノセントに振る舞ってしまうと、社長としての自分という適切なポジショニングができずに、国内で成功し嘱目されていた人がボロボロになって帰ってくるというケースがかなりあります。日本でいう年功序列や、会社の中のヒエラルキーといったものは、外へいくとほとんど意味を持たないといって良いでしょう。「俺は社長だ」と威張っても、みんな頭を下げるわけではなくて、自分たちにとって役に立つ人であるかどうかで判断されます。
――自分の軸があると同時に、それを現地でつくり直すくらいの気構えでいくわけですね。現地では、これまでの常識が通用しない。
文化の多様性、民族の多様性に、日本ではある種の偏見をもつような教育をされるし、もっといえば、日本のいろいろな書物を読んでアジアに行けば、なんとなくアジア諸国の人たちを見下すような感じになってしまう。そのような自分がこれまで育ってきた教育やキャリアの呪縛から一度自分を解き放って、「本当のところは何なんだ」と勉強し直すような探求心をもった人がうまくいくのではないかという気がします。
――大澤さんご自身の海外でのご経験について教えていただけますか。日本興業銀行に入行されたのち、IBJインターナショナルの副社長としてロンドンに赴任されたのが海外勤務の最初でしょうか。
その前に、3カ月間だけトレーニーで行ったことがありますが、本格的に赴任したのは38歳のときで、IBJインターナショナルの副社長としてロンドンに行きました(1979―1983年)。当時はまだ30人くらいの規模でしたが、1988年に同社の社長として赴任したときには、ジャパンマネーで大きくなって、300人くらいの会社になっていました(~1993年)。それらの海外経験を通じて学んだのですが、海外で仕事するときに何がいちばん大事かというと、昔の言葉でいえば、裃を脱いで組織作りを一からやるということだと思うんですよね。
――組織作りを一からというのは、実際にどのようになさったのですか。
IBJインターナショナルの社長になったとき、私自身の下にそれぞれの営業フロント業務を担当するディレクターが複数いたのですが、一人を除いて日本人だったのを、すべて外国人に替えました。
新しい体制では英国人、ロシア系フランス人、イラク人、ドイツ人、オランダ人そしてアメリカ人と、ディレクターの国籍がみんな違いました。
――それこそダイバーシティですね。当然本社とのコンフリクトは起きますよね。横やりは入りませんでしたか。
まず、前任のディレクターだった日本人たちに、「うちの会社がこれから先もう一歩、二歩伸びて、現地でもちゃんとした会社になるためには現地人に任せることが必要だよね」と言って、その人たちには納得してもらいました。ところが、本社から見れば「とんでもない」という話になる。本社からの指示が伝わらないことから始まって人種的な偏見まで、いろいろなごたごたも起きました。私自身は、興銀のような大きな組織にても、若い頃から人がやらない新しい分野の仕事をもっぱらやってきたということもあって、新しい仕事に相応しい組織をどう作っていくかには、それなりの流儀が確立していたようにも思います。「ここのトップに指名したんだから、俺にまかせろよ」と(笑)。指名されたトップがミッションを果たすこと、それが大きな軸なのではないでしょうか。
それまでのIBJインターナショナルは日本の出先であって、ロンドンのインベストメントバンクとしてのIBJインターナショナルではなかったわけです。ロンドンのシティにあるIBJインターナショナルとして、クライアントからちゃんと頼られる会社になるかどうか、新しい体制作りの応援団はクライアントだけなんですよ。会社というのは誰に食べさせてもらっているかというと、本社でも現地の幹部でもない。クライアントに食べさせてもらっているわけです。そういう人たちが望んでいる体制を作ると言えば、これはもう誰にも文句は言えない。
◆「日本」を意識する?しない?
――どちらを向いて仕事するか、つまり、本社を向いて仕事をするか、現地のお客さんに向かって仕事をするか、ということですね。
解は本当に簡単なことです。ただ、そういうときに、お客さんが言っていることがちゃんと聞こえるような自らの穴を空けるということも大事なんです。ときに「お客さんのことは、あなたは手を触れないで下さい。私に任して下さい」と、現地人のボスみたいな人が邪魔をすることがありますから。
――お客さんからの声が聞こえるようにする、ということと共に、社内での情報チャネルをしっかりもっておくということも、海外では特に大事です。
社内の情報に関しても、何かあったときに、組織の正式のルートからくる報告を待てばいいだろう、と思っているととんでもないことになります。ロンドンで何度も失敗や事故が起きましたが、ラインにいる直属の部下や日本人の副社長から報告がくるのはだいたい2、3日後でした。「大澤さん、まだちょっとご報告していませんでしたけれど」と言うから、「ああ、一昨日の話か」と(笑)。
正式な組織のチャネルも大事だけれど、こと悪い情報に関しては、リーダーはまったく別のチャネルを持っていないといけません。
――話は少し変わりますが、大澤さんご自身は、海外にいるときも、「日本のために」ということを意識されることはありますか。
「日本」をどうするかということは、選挙民としては大いに興味があるけれど(笑)。現在、たとえば任天堂やソニー等々の多くの大企業では売り上げや収益の過半、企業によっては7割、8割が、海外から得られています。こういう時代に、日本の国益とは何を意味するのでしょうか。日本の国益と派遣された国の国益とは当然ちがう。だから、そういう矮小なことを考えないで、こと事業を遂行していく場合には「世界市民として」と考えた方がいい。
先にIBJインターナショナルのディレクターを日本人から外国人に替えた、というお話をしましたが、そうなってくると、日本のための日本の会社と思っていると、すぐに限界に突き当たってしまうのではないでしょうか。
◆製造業のグローバル化と金融業のグローバル化
――今日お聞きしたいことの一つは、製造業のグローバル化と金融業のグローバル化の違いなのですが、今伺った、「顧客に価値を提供する」というところは共通ですよね。それを前提とした上で、金融の世界でのグローバル化と製造業の世界でのグローバル化とで、もし質の違う部分があるとしたら、どんな点が違うのかということを教えていただきたいのですが。
製造業のグローバル化と金融業のグローバル化は、実はそれほど大きな違いはありません。むしろ、昔の金融と今の金融の違いのほうが大きい。東京勤務の頃(1980年代)に、銀行のプロダクツとサービスを引っさげてカナダ、オーストラリア、ヨーロッパなどのドサ周りをやりました。興銀が買ってもらいたいプロダクツを一生懸命営業して回ったのだけれど、当時は、何十回通ってもほとんどふりむいてくれませんでした。
ところが、プラザ合意(1985年)のあと金融(資本)の自由化が進み、いわゆるプロダクツ・ポートフォリオ(金融商品の品揃え)が大幅に増えました。それで、「このお客さんにはこれだよね」というのをお客様のニーズにあわせて持って行ったら、一度で商談成立ということになりました。そのころロンドン支店長だった人が大喜びして、「やはりマルチプロダクツのIBJインターナショナルを作ったおかげだ」と喜んでいました。
製造業も、まったく同じことだと思うんですよ。プロダクツ・アウトで、日本のスペックで物を売ろうとしても、たとえば現地のお客さんには高すぎて買えないということがある。一方、たとえば携帯電話で、「中国のお客さんが買うのは5万円くらいのものだろう」と思っていたら、実はデザインのよい10万円の機種が即日完売だった、という話がある。本社の頭で勝手に解釈していてはだめなんですよ。先の金融のプロダクツと同じで、現地で、「この人は何を欲しがっているんだろう」というのを見極めて、それをマーケット・インで持っていく。そういう点では、製造業も金融もそれほど違いません。
◆この15年、20年で金融の世界に起きたこと
ただ、ここ15年、20年の世界の金融というのは、いろいろな意味で間違いをおかして、その結果、サブプライムの問題やリーマン・ショックが起きたということがあります。
――具体的にどのような部分が間違いだったのでしょうか。最近もアメリカで、金融の規制強化がされることになりましたが。
最近新聞などで報道されている金融制度の見直し、再規制は当然のことと思います。
金融業界の収益の構造は、90年以降に大きく変わってしまいました。それまで金融業というのは、いわゆる利鞘やフィー、コミッションで稼ぐビジネスでした。しかし、90年代以降に、欧米の投資銀行やメガバンクは皆、世の中の動き、相場のうねりをみて自分でキャピタルにレバレッジをかけて、自ら相場を張って、自分が投資家になってしまった。
サブプライムの問題についても、最初は、錬金術みたいなストラクチャー商品をつくってお客さんに売っていたわけですがそのうちに、これを手持ちにしているとずいぶんサヤが抜けるねとか、インカムゲインがあるね、ということで、在庫を大量にかかえてきた。この在庫資金の調達ができなくなって今回の金融危機が起こったわけです。
90年代以降、金融業は自分のキャピタルにレバレッジをかけて相場を張ることによって、粗利の8割、9割を生み出すようになった。それで、汗水たらして発行引き受けや債券の売買、エクイティの売買をやっても、これらの手数料収入は、せいぜい全体の15%くらいにしかならなくなったわけです。そして、この自己売買による85%の収益が、ほとんどそれを担当しているプロッフェッショナルといわれる人たちのポケットに入ってしまった。
やはり金融の原点というのは利鞘とフィーではないでしょうか。お客さんが借りてくれる、お客さんが売買してくれることが原点であり、そこに一番社会的なバリューがある。しかし、90年代以降は、インベストメントバンクがこぞって上場を果たし、収益追求の体質が定着し、しかも金融の自由化が火に油を注ぐ結果となって、業態を超えた金融機関同士の大競争時代が始まったわけです。この20年は世界的な金余り現象が加速して、もうけのオポチュニティが圧倒的に市場にあったので、みんなそちらに雪崩を打っていったということではないかと考えています。
私がロンドンにいた88年~93年頃というのは、まだまだ及び腰でポジションを張っていた頃ですが、そこからあとは、すべての大手銀行、すべての大手投資銀行が、賭博場に集まって商売をしていたようなものです。
――私(留岡)はその頃、香港のソニーにいて、テリトリーがアジア全部でした。ところが97年にタイで通貨危機が発生して、韓国などの代理店が資金ショートを起こして、バッタバッタとつぶれた。あのときに私が感じたのは、「こういうときこそ、お金を貸してほしい」ということでした。
そういうときに、ちゃんとお金を貸せるだけのリスクテイク力をもてるようにということで、資本金規制ができたのだけれど、普段はそのお金は使われないで眠っている。それなら、これにレバレッジをかけて相場を張った方が良いじゃないかということになって、みんなそちらに傾斜してしまい、サブプライム危機のようなことが起きてしまった。
――香港時代には、その97年のときに資金ショートでたくさんの代理店がつぶれて、それをリカバーするのに数年かかりました。新陳代謝という意味ではよかったのですが。
金融というのは、結果としてゾンビを振り落としていくという機能があるので、その機能は全面的に否定されるわけではないけれど、金融危機のときに一番先にお金がなくなったのが世界一の銀行シティ・バンクだったということでは、誰を頼りにすればいいんだということになる。
このように金融は20年前と今とで全く変わってしまっています。ただ、ご存じのように今、グローバリゼーションからリージョナリゼーション、地域主義が出てきている。EUはこうだ、南北アメリカはこうだという具合に、だんだん地域の利害が一致してきて、それを主張するようになる。そうなってきている現在、もういちどメーカーと同じような目線で、その地域の金融を応援しないといけない。その地域にどんなニーズがあって、どういう仕事をすれば、ちゃんと自らのキャッシュフローで拠点を運営できるかを考えていくということなのではないかと思います。
◆社長の役割は「ノー」ということ
――90年代の金融業界の大きな変化について伺いましたが、このような中で個人が、自分なりの矜恃をもちながらやっていくということはできるのでしょうか。自己確立ということとも関係すると思いますが、大澤さんご自身はどのような矜恃あるいは信念をもちながら仕事をなさっていたのでしょうか。
少しあとの時代、つまり興銀証券、みずほ証券の運営していたときに、私はこうした信念をもちました。かつての金融機関というのは、ソニーや東芝、パナソニックといった資金調達者である企業がお客さんで、投資家というのは正面のお客さんだとは思っていませんでした。投資家というのはある条件で発行された債券やエクイティ(株式)を買う人ということで、販売業務のことを「ディストリビューション(配る)」という言い方をしていた。93年に興銀証券ができたときに過当競争の中で何を以って新しい会社の存在意義を主張できるかとして考えたのが、投資家を正面のお客さんとして大事にする会社にしようということでした。日本興業銀行というのは、もっぱら資金調達者(企業)をお客様と思っている銀行でしたから、こっちは投資家を大事にする証券会社にしようじゃないかと。
それで資金調達者には、「投資家はあなたの会社をこう判断しています」と伝えることにしました。そのころは、格付けなどはまだ普及していませんでした。だから、たとえばソニー、パナソニックとサンヨーで、資金調達コストに差をつけるというようなことは許されなかった。電機業界だったらみんな一緒とか、鉄鋼業界だったら一番でも五番でも同じ条件ということが当たり前でした。それを、「投資家は御社をそう見ていません。御社の財務体質だと、これだけ余計にはらってもらいたい」と伝えるようにしました。それが6、7年経ったら当たり前のことになりましたが。
興銀証券ができて4年くらい経った97年頃から、銀行が「貸しはがし」をやり始めます。それで、企業が銀行からお金を調達できなくなったときに、「それでは、債券(社債)を出してあげましょう。ただし、投資家はこういう条件と言っていますから」と、その条件を呑んでもらうようにしました。それまでは、社債の発行というのは、日本全体で年間で1兆円規模だったのが、97年は10兆円くらいになりました。
そのときに、証券大手4社が、総会屋への利益供与でペナルティ・ボックスに入っているものだから、新規参入であるわれわれ興銀証券が新しいプライシングの手法を持ち込んでも、どんどん仕事がまわってきたということがありました。
みずほ証券の社長時代には、サブプライムのようなストラクチャー商品で相場を張っていた人に、全部ポジションをクローズさせて、という荒療治をやりました。持ち株会社からはずいぶん収益へのプレッシャーは掛かっていましたが(笑)。
――そこに矜恃があるわけですね。
社長しか「ノー」と言えません。部下はみんな、「これはもうかりますよ。こういうオポチュニティがあるからこれだけ相場を張りましょう」みたいに言うけれど、「それはダメだ」と。社長は、「イエス」と言うことより「ノー」と言うほうが大事です。サブプライム問題で、世界の大手の金融グループのうち二つだけがあまり傷ついていない。その原因は、その二行のトップが、先行き不透明なストラクチャー商品のポジションを手仕舞いましょうと言ったということがある。「ノー」と言うことは、絶対にリーダーシップが果たさなければならない役割です。
◆リーダーは勉強しないといけない
――いま日本において、「リーダーが欠乏してきている」と言われています。それで、リーダーをどうやって育成するか、という議論が出てくるわけですが、大澤さんのそのあたりのお考えをお聞きしたいと思います。私もいろんなところで、このことは聞かれますので。
リーダーは勉強しないといけません。スキルを勉強するのでなくて、世界の流れを勉強しないといけない。「明日相場がどうなるか」というのはディーラーの仕事であって、リーダーの仕事ではありません。リーダーは半年先、3年先を見、5年先を見る。そういうことのために、世界のgeopolitics(地政学)から始まって、いまでいえばお金の流れや、消費の流れなどを勉強していかないといけない。私はときどき中国に行きますが、中国人は政府の官僚から大学教授、学生に至るまで、日本人の10倍くらい勉強しています。過去の歴史、とくに失敗の歴史をよく勉強している。
ハーバード流というのか、スタンフォード流というのか、リーダーシップについてMBAなどでは科学的に分析しようとしていますが、ああいう種類のことだけでは、リーダーシップというのは育たないと私は思います。教科書のチェックボックスに印をつけながら、「俺はこれだけやっているから、リーダーとして安心だ」などということはありません。
リーダーは、世の中の流れを知らないといけない。リーダーというのは、言い方を変えれば、戦争のときの大将であるわけで、大将としてちゃんと勝てるかということなんですよね。まず、敵の戦力を測るということから始まって戦況をきちんと見られるかが問題です。多くの戦争は、自然条件の変化によっても失敗しています。ナポレオンがロシア遠征で“冬将軍”と呼ばれる厳しい気象条件で敗れたことはよく知られているとおりです。それは何を意味するかというと、「相手」だけを見ていればいいということでなくて、自然環境つまり地形はもちろん季節の変化まで全部戦略に入れて戦うということ。人間が組織をつくって何かをやろうとするときに、どういうファクターが一番影響するのかというところにまで、きちんと自分の目が行きとどいているかどうか。そのために、勉強をしないといけない。
――リーダーは、俯瞰する視点を持たないといけないということでしょうか。
そうです。「お客さんのところに社長が行くと、大型商談ができるから」なんて言う人がいても、私は聞きませんでした(笑)。部下はおうおうにして、リーダーの使い方を間違っています。「社長も行ったけれど、だめでした」と失敗したときの言い訳にするために、社長を商談に引っ張り出したりする。
そうではなくて、社長というのは、戦争をどういうタイミングでしかけるかというような大きな判断をする人であるので、ヒマにしておいてもらわないと困るわけです。やはりリーダーにとって一番大事なのは即決できるかどうかで、「ノー」と言うのでも、「ちょっと一晩考えるから」なんて言っている余裕はない。なぜ即決できるかというと、日頃から勉強していて、戦況を高いところから眺められているからです。
◆グローバル・リーダーには何が必要か
――リーダーに必要なのは勉強することであり、資質としては俯瞰できること・即決できること、と言えそうですね。グローバル・リーダーということだと、それに加えて何が必要でしょう。
いまグローバル・リーダーとして何が必要かというと、収益が8割海外から来ているのだったら、社長たるものは8割の時間は海外を見ておかないといけない。ところが、経団連の会合があるからとか、取締役会、株主総会があるから等々、なにしろ出不精の人が多い。
――日本企業で、海外部門は海外担当取締役に任せている、という例も見受けられます。グローバルはこの人に任せたから、ということでは、やはりまずいということでしょうか。
海外担当取締役が俺のボスだ、とはみんな思っていません。会社の最終決定権は社長にあるとみんな思っていて、社長を見て仕事をしています。ナンバー2以下というのは、みんなリーダーに責任をヘッジできるから、高みに立った視点でものを見ていません。高みに立ったリーダーというのは、必ずそこのところを満足させるだけの知見と決断力をもっていないといけない。
海外担当が8割の時間、海外に出ているのなら、百歩譲って社長は3割でもいいけれど、3割というのは、1年の3カ月以上外にいないといけないということで、これでも日本人にとってはけっこうたいへんです。でも、欧米の会社にとってはそれが当たり前で、社長がいつも本社にいるというようなことはあり得ない。
――日系企業のいまの状況は、海外売上げが国内より多くなっているにもかかわらず、トップマネジメントが海外を向いていません。いま起こっている問題のひとつは、現地の拠点で雇ったローカル社員がいつかないということです。本社の海外担当に意思決定をうながしても、なかなか決定してもらえない、それで失望して辞めるという問題が頻繁に起こっています。日系のグローバル企業の人事の方とお話をすると、そこに話がいきつくことが多いのです。この問題に対してどうしたらよいのか、ということを最近考えているのですが。
これはやはり、現地のローカル社員を本社の役員にするという、昇進のしくみをきちんとつくる。わかりやすい例でいうと、ソニーのストリンガーさんは、米国法人の会長を経て、本社の社長になりましたね。この間辞任してしまいましたが、日本板硝子の社長に、子会社である英国ピルキントンの社長が昇進したというケースもありました。こういうしくみを多くの会社がつくるべきです。
というのは、リーダーを育てるには、現場を踏ませることがやはり大事だからです。アメリカの会社というのは、ブランチ(支店)というのはなくて、全部独立したオペレーションの会社になっていて、それぞれ社長がいる。そこで社長を務めた人が、本社のディレクターになることもあるし、野戦に強い人はそのままそこの社長で終わり。退職金を沢山渡して「さようなら」という場合もある。そういうルートが日系企業にもできて、それが明示されていれば、有能なローカル社員が途中で辞めるはずがない。ミッションをはっきりさせて、昇進のしくみをきっちり作ることが肝心です。
――いま日本企業は人数が過剰で、日本人社員にとっても、ポジションがないということで、閉塞感がありますよね。そのなかで、海外赴任や、子会社の社長という形での抜擢というのは大事だと思っています。そこでタフ・アサイメントを乗り越えていく。そういうステップで社長までいく。そのようなキャリアパスがとても大事だと思っています。
その通りですね。リーダーを育てるというのは、戦いの場に出し、責任をもたせる、ということしかありません。海外でタフ・アサイメントを乗り越えて来た人、そういうキャリアパスを通ってきた人をきちんと昇進させるということがいちばん大事で、それは海外人材の本社登用と両輪です。
◆「アカウンタビリティ」とはみんなの前でいうこと
――先ほど出た、「ミッションをはっきりさせる」ということに関係する話ですが、日本企業では、ポジションは言われても、ミッションははっきり伝えられない、ということがありますよね。
そのとおりです。日本企業では、「シンガポールに行ってこい」とは言っても、「何をやってこい」とは言わない。「お前、シンガポールの社長にするから」と言われて、「かしこまりました」で終わってしまう(笑)。海外企業であれば、CEOは「シンガポールがいまこういう状態で、俺はこういうことに満足していないから、お前を派遣するんだ」という言い方をします。それと同じことを、日本企業が外国人に対して行っていますか。社長の背中を見て育てよ、なんて言ったって、海外の人は、背中なんか見ても学習しませんから(笑)。
――言語が違う分、よけいにきっちり言葉にして伝えないといけないわけですね。
ミッションを伝えるときに、もう一つ大事なのは、本人にだけ言うのでなくて、みんなに伝えるということです。たとえば、ある人を部長に指名したときに、みんなの前で「この人には部長としてこういうミッションを与えたから、みんな一生懸命サポートしてくれ」ということを言わないといけない。本人だけ別室に呼んで、「こんどお前を部長にしてやるから」と伝えて、その人が帰ってきて「おい、部長になっちゃったぞ」と言っても、下の人はサポートしません。
みんなの前で「社長の私が決めた」と言わない限り、だめなんですよね。最近、「アカウンタビリティ」という言葉が流行っていて、説明責任と訳されているけれど、別室で説明してもだめなのです。パブリックリーにみんなの前で説明してはじめて、アカウンタビリティが達成される。
◆人の心の機微がわかること
――大澤さんご自身は、新しいポジションを提示される度に、ミッションを与えられてきたという感じでしょうか。
私は、「お前これ任せたよ」というようなことは、実は一切言われたことがないのです。あとから見てみれば、付託に応えた、というように見えるのかもしれませんが。
――外部から言われてというより、最初のお話にあったように、自分の軸を常にもっていたという感じでしょうか。
自分が何かやっているときに、気負うことはまったくありませんでした。IBJインターナショナルの社長になったときにも、興銀証券、みずほ証券の社長になったときにも、自分で心に誓ったのは、「仕事をしている人がワクワクする会社にしよう」ということでした。実際、IBJインターナショナルでは、中途採用して主要ポジションにつけた人が入社して3カ月経った頃に、「会社にくるのがこれほどワクワクすることはいままでにない。土日だって、来週何をしようかと考えるようになった」と言ってきてくれたことがあります。
――すばらしいですね。
一つの部署で何かあると、違った部署の人もそこに集まって議論に参加する。「何か起こっているぞ」と集まってくる。それが本当に面白かった。
――そういう空気をつくるコツというか秘訣は、何かあるのでしょうか。
現場に僕が降りていく。今、暇そうだなと思うと現場に降りていって、いちばん暇そうにしている人を、後ろから羽交い締めにしたりする(笑)。
――かつてはソニーでも、井深さんや盛田さんが、気がつくと自分の後ろに立っていた、なんていうエピソードがありました。これはソニーにいる僕の友人から聞いた話なのですが、彼はビデオのデッキのドラムという、テープの巻き付く回転部分の設計を担当していた。どうやったらできるだけなめらかに巻き付けられるか、ということをやっていて、あるときふと気がつくと井深さんが立っている。そして井深さんがそのドラムを手にして、ペロリとなめて、「うん、これはなめらかだ」と言ってくれたという。彼はそれに感激して、その後、火の玉のごとく設計にいそしみました。トップのそういう姿勢が、現場にとっては何よりの励ましになります。
私が現場をまわっていたというのは、もう一つ意味があります。取引で損を出している人というのは、目を伏せるのです。自分が稼ごうと思って買ったものの値段が下がっていると、私が来ると目を伏せる。そういうときは、あとで部屋に戻ってから、その目を伏せていた人の隣の席の人に電話して、「隣が目を伏せているけど、だいじょうぶか」。「大澤さん、実は彼は損をしているんですよ」。それでそのあと、「お前、心配するな」と、背中を叩きに行って、しこったポジション損切りの指示をする。ほっとした顔を見るのもトップ冥利に尽きるということでしょうか。
――そういう、人の心の機微がわかることというのも、リーダーには大切な資質ですね。
人の心の機微がわからないと、鬆の入ったような報告書をもらっても、真実とほど遠かったりしますので。
――最後に、メンター制度について伺いたいのですが、社内だと言えない悩みも、外部のメンターになら言えるということがあります。日本の良いところのひとつに、師範と弟子の1対1の関係のような濃密なあり方があるので、それを外部メンター制という形で、企業に提案できないかなと思っているのですが。
私自身はそれまで自社内で誰もやったことのない仕事をやってきたということもあって、仕事を教えてもらったのは興銀内部の人でなくて、証券会社の人、つまり外部の人でした。しかし本当に難しい仕事に立ち向かったときに、ストレスが高じて自律神経失調症に罹ってしまいましたので、そんなときにメンターがいれば、どれほど救われたかとは思いますね。
メンターということではありませんが、宴席などで謦咳に接した他社の社長たちの生き様を見たということが、私にとっては勉強になりました。それを仕組みのなかでやっていくとしたら、外部メンター制度ということになるのかもしれませんね。
英国の経営学者チャールズ・ハンディは多くの経営者のメンターをやっている方ですが、彼の著書『The Hungry Spirit』という本に、「proper selfishness」という言葉がありますが、自己(適正な自我)確立した方で、私心なくメンターをやってくれる人がいるかどうかがポイントでしょうね。
(収録・2010年1月27日)